和洋女子大学では2026年4月に「AIライフデザイン学部 AIライフデザイン学科」を新設する。AIの開発ではなく、使いこなし方を身につける斬新な学部だ。和洋女子大学の既存学部・学科で蓄積した知見とも結びつけながら、これからの時代を生きる力を磨いていく。教員の専門も多岐にわたっており、元ジャーナリストながらAIに携わる仕事をしてきた人もいるそうだ。新学部に期待することや予定している授業などを、AIライフデザイン学部アドバイザーであり、教員就任予定の南龍太先生に伺った。
「これからはAIの時代になる」未来を見据えた新学部
今や、AIに関する話題を見聞きしない日はない。
AIは私たちの社会や生活に深く浸透し、さまざまな変革をもたらすと同時に、新しい仕事や価値を次々と生み出している。
こうした時代の潮流の中で、「AIをどう活かし、より良く生きるか」を探究する新たな学部が、和洋女子大学に誕生する。それが「AIライフデザイン学部」である。
この学部は、AIの開発やプログラミングを専門とする学部ではない。
和洋女子大学が長年にわたり培ってきた人文学や家政学の知を基盤とし、「人」や「社会」、「それらを取りまく環境」といったライフデザインの視点から、AIやデジタル技術を融合させ、新たな価値を創造することを目的としている。
各分野の専門教員は、自らの研究にAIやテクノロジーを積極的に取り入れ、その実践知とともに、AIを有効活用するための知識や方法論を学生に伝授する。
学生には、生成AIをはじめとした最新のソフトウェア環境が提供される。自身の興味に応じて、ライフデザインの中から特に深めたいテーマを選び、AIやデジタル技術を駆使しながら、4年間の学びを構築していくことができる。もちろん、AIや情報技術そのものを中心に学ぶことも可能だ。
教員それぞれの専門性と、学生一人ひとりの関心が融合され、専門性と好奇心が交差するこの学びの場では、今までにないAIの活用方法が生まれるだろう。
「未来をどう生きるか」を主体的に考え、AIを手にした自分らしいライフデザインを描いていく。これからの未来を、自分の手でデザインしたい―そんな人にぴったりの学びが、ここにある。

学生時代の専攻はペルシア語!教員の経歴も学生のモデルケースに
AIライフデザイン学部には幅広い分野の教員がいる。今後も学生の関心に応じて、さまざまな領域の専門家を招く予定だ。学部開設と同時に就任を予定しているのが南龍太先生。大学時代はペルシア語を専攻し、卒業後は石油会社や新聞社で勤務した。その後も外資系コンサルタントやシンクタンクの研究員など、分野を超えて活躍している。
「もともとは国際協力に関心があり、イランやアフガニスタンなどで使われているペルシア語を学びました。新聞社に入ったのは2011年で、長く担当したのは経済部。東日本大震災の被災地の取材なども担当しました。その後家族の都合もあってアメリカで生活しましたが、新型コロナウイルス流行をきっかけに帰国して、リモートワークがしやすい環境を重視し、AIやICT分野のトレンドを探るシンクタンクの研究員になりました。教員になろうと決めたのは、和洋女子大学のチャレンジ精神や、わかりやすくAIを伝えたいという想いに動かされたからです。」
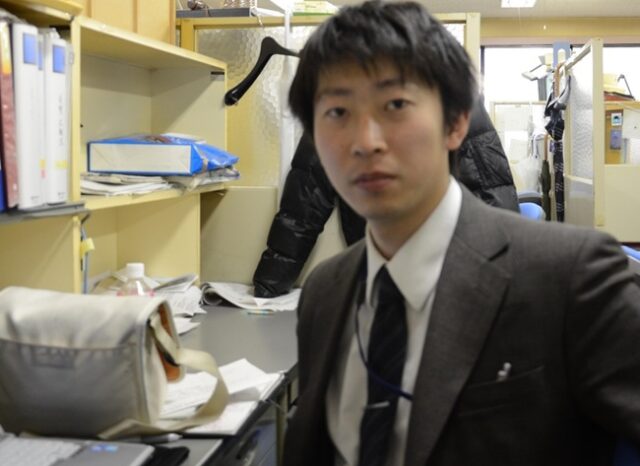 共同通信社で記者として活躍されていた南先生
共同通信社で記者として活躍されていた南先生
南先生の経歴は、文系でもAI分野の専門家になれることを体現している。AIや情報技術の専門的な研究をはじめ、国際協力、メディア、経済、デジタルなど携わった分野が多岐にわたる点も、「ライフデザインの各分野でAIを活用し、新たな価値を生み出し世の中を変える人を育てたい」という学部設立の目的にぴったりだ。
また、先生の生き方そのものが学生に刺激を与えるのではないかと、和洋女子大学も期待を寄せている。変化が激しく先行きが不透明な時代を生き抜くためには、ときにフィールドを変えながら自分自身を磨く姿勢や、積極的に挑戦する行動力が必要だ。南先生と接した学生は、卒業後の人生を切り拓く力も伸びるだろう。
教員就任後、南先生は社会やAIの変化を伝える授業を担当する予定だ。1、2年生向けにはAIの活用方法や、演習、情報通信技術についても担当する。3、4年生には各自の興味とAIを組み合わせ、さらに深める方法を伝えるつもりだという。
「AIのトレンド分析に携わる前は新聞記者もしていたので、文系の人にもAIをわかりやすく伝えられると思います。私自身も学生と一緒に学びながら、授業や研究をしていきたいです。」
将来やりたいことが決まっていなくてもいい
AIライフデザイン学部は、AIに興味がある人だけでなく、まだ進路が定まっていない人も大歓迎だという。間口の広い学部をめざしたいと、南先生は語った。
「授業は間口を広くしたいと思っています。人文や家政に興味がある人はもちろん、何をしたいかわからない、といった人にも多く来ていただきたいです。様々な分野の学びの中でAIを活用することで、自分の興味がわかっていくと思いますし、AIが新たな関心を引き出してくれるかもしれません。卒業までの間に、この分野では誰にも負けない、と思えるものを持てるよう、しっかり伴走していきたいです。」
新学部の設立にあたっては、大学のOGが勤務している企業をはじめ、各分野の企業に取材を行い、これからの社会で求められる人材像についてその考えを聞いている。取材内容はHPでも紹介されており、AIライフデザイン学部の学びを修めた学生への大きな期待もうかがえる。
また、和洋女子大学の「女子高校生のための『大学での探究』体験講座」では、授業の一端を体験することができる。8月6日(水)午前はボッチャというスポーツでAIと対戦してAIを身近に感じることのできる講座、午後には博物館におけるデジタルやAIの活用を学びながら学芸員体験のできる講座、8月7日(木)午後にはAIの助けを借りながら自分のパーソナルカラーを探すことができる講座を実施予定だ。未来の生活をいち早く感じられる学びに、飛び込んでみてはいかがだろうか。

和洋女子大学 AIライフデザイン学部アドバイザー
南 龍太
新潟県出身。東京外国語大学ペルシア語専攻卒。政府系エネルギー機関から経済産業省資源エネルギー庁出向の後、共同通信社記者として盛岡支局勤務、大阪支社と本社経済部で主にエネルギー分野を担当。渡米後、外資系コンサルティングファームを経て現在は情報通信大手のシンクタンクにて研究員として務める。著書に『AI・IC・5G業界大研究』、『エネルギー業界大研究』(いずれも産学社)、『グローバルITの世界地図』、『ITの仕事に就いたら「最低限」知っておきたい 生成AIの常識』(いずれもソシム)、『未来学』(白水社)、『外国人のあたりまえ図鑑』(WAVE出版)など。

