昨年、一部の私立大学で実施された学力テストのみによる学校推薦型選抜が大きな話題となりました。それは学力テストを2月1日以前に実施することが、文科省通知で示したルールを逸脱するとされたからです。受験の常識から見れば「何を今さら」感はありますが、今後、年内入試での学力テストが禁じられてしまうと、学力チェックの方法がかなり限られてしまいます。入試制度そのものに関わる問題のため、今後の行方を多くの関係者が注目しています。

昨年、話題となった学力型年内入試
一般的に総合型選抜、学校推薦型選抜のいわゆる年内入試は、小論文や面接などを中心に選抜が行われます。ここで「いわゆる年内入試」としているのは、国公立大学で大学入学共通テストを課す方式の場合、面接などは年内に実施していても合格発表は大学入学共通テストの結果が出る2月になるケースがあるからです。一般的に年内入試とは、年内に入試実施と合格発表が行われることを指しますので、ここでは「いわゆる年内入試」としています。
実は意外にも入試のルールブックと言われる、文部科学省「大学入学者選抜実施要項」では、年内入試でも学力検査を行っても良いとされています。ここで言う学力検査とは、個別学力検査(一般的な学力テスト、いわゆるペーパーテスト)、大学入学共通テスト、小論文・面接・実技試験等、資格・検定試験の成績などです。つまり、今回問題になった個別学力検査を課すことは年内入試で禁じられているわけではありません。ただし、個別学力検査の実施は「2月1日~3月25日まで」とされていますので、その点がルールの逸脱だとされたのです。
ちなみに「大学入学者選抜実施要項」は毎年のように記述内容が変わります。その前年版を見ると、総合型選抜では「各教科・科目に係るテスト」を活用しても良いと書かれており、学校推薦型選抜では「学力検査の免除又は負担の軽減を図り」と書かれていました。つまり、学力型の年内入試は許容されていたわけです。内容が年度更新された「大学入学者選抜実施要項」は、毎年6月に通知されます。しかし、私立大学の場合、5月初旬には次年度の入試概要を発表しますので、基本的には前年の「大学入学者選抜実施要項」に基づいて、入試制度を設計します。そのため、今回のような大きな変更が6月に通知された場合、言わば、後出しジャンケンになりますので、大学も高校も現場としては非常に困るのです。
すでに2026年度の年内入試概要を発表した大学も
いずれにしても、今回の話題の中心は東洋大学と大東文化大学ですが、その東洋大学の学力型の学校推薦型選抜(指定校ではなく公募制)は、新聞報道によると約2万人の志願者を集め、合格者は約4千人、倍率が5倍弱と受験生から多くの指示を集めていました。そして、これも新聞報道ですが、来年2026年度入試でも同様の形式の入試を実施することが公表されています。ただし、変更点があります。現在の学校推薦型選抜から総合型選抜に変更し、学校長の推薦書が不要になります。そして、英・数または英・国の学力テストに調査書やその他の評価方法を組み合わせることで、学力テストのみではない、多面的で総合的な評価にする方向で検討されています。さらに、次の点がなかなか挑戦的なのですが、試験会場を自大学に加えて、札幌から福岡までの主要都市にも設ける方針です。
実質的には拡大路線ですので、このような入試制度にすることで、行政からまた圧力を受けるのではないかと東洋大学のことが心配になるのですが、実は事態は進展しているようです。そのヒントとなるのは、文部科学省「大学入学者選抜協議会」における議論です。文部科学省のHPで公開されている議事録は3月13日が現段階で最新版ですが、これを読むと非常に興味深い内容となっています。
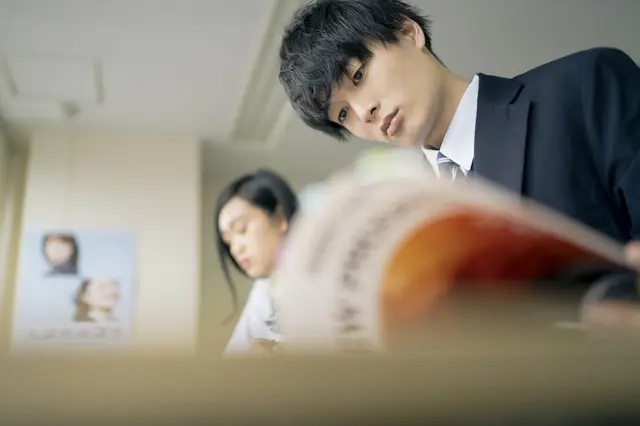
「基礎・基本的な知識を問うテストは問題ない」が共通認識
会議では大学関係団体(国立大学協会、私立大学連盟など)と高校関係団体(全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会など)からの意見が示されています。その中でも日本私立大学連盟からは、大学教育を受けるために必要な能力を把握するために、従来からも活用するように言われてきた、「小論文、プレゼンテーション、口頭試問、実技や資格・検定試験の成績等を学力把握に活用するにしても、これらの方法では、各教科・科目に係る基本的な知識等を十分に把握・評価することは困難である」と真っ当な意見が出されています。
そのうえで、日本私立大学連盟は「総合型選抜は調査書、学校推薦型選抜は調査書及び推薦書に加え2種類以上の評価方法(小論文、面接、実技検査等)を適切に組み合わせて丁寧に選抜を行うこととし、その評価方法の1つとして、教科科目に係る基本的な知識を問うテストで基礎学力を把握することも認めて頂きたい」と提案しています。関心のある方は是非、議事録を読んでいただきたいのですが、途中の議論を省略すると、多面的・総合的な評価を丁寧に行う選抜であれば、複数ある評価方法の1つとして、教科科目の基礎・基本的な知識を問うテストは実施しても構わないというのが、この時の会議における共通認識であり、結論です。
ただ、この他にも、総合型選抜は併願が認められるが、学校推薦型選抜は1校受験の専願にすべきだ、大学入学共通テストが始まった時点ですでに学力テストが始まっているのだから、大学入学共通テスト実施後は2月1日からと言わず個別学力検査の実施を認めても良いのではないか、と言ったリアリティのある意見も出されています。これらのことから会議では実のある議論が行われていたことがうかがえます。
【文部科学省】大学入学者選抜協議会
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/112/index.html
公募制の学力型学校推薦型選抜は全て総合型選抜になる?
これから引き続き、大学入学者選抜協議会で議論が行われて、細部が詰められていくと思いますが、現段階の情報から考えると、今回、問題とされた学力型の年内入試は継続実施が可能ですが、次のようにいくつかの変更が必要になりそうです。
まず、公募制の学校推薦型選抜ではなく、総合型選抜として実施することになります。そして、学力試験は実施できますが、出題範囲や問題の難易レベルが基礎的な内容をチェックするものになっているなど、受験生に対する配慮が必要になります。加えて、学力試験以外の“何か”を足さなくてはいけません。この“何か”はアドミッションポリシーと関連付けて説明する必要がありますので、各大学の担当者のセンスが問われるところになります。
ただ、前述のように2万人規模の志願者に対して面接を実施することは現実的にできません。そのため、調査書を点数化、つまり学習成績の状況(旧、評定平均値)を加点することも方法の1つとなります。その場合、オール5の評定の場合は「5.0点」ですので、英語100点+国語100点+調査書5点=満点205点の入試制度でもルール通りになります。しかし、さすがにそれでは挑戦的過ぎますので私が担当者だったら怖くてできません。そこで「小論文、自己推薦書を出願時に提出して評価の対象にするが点数化しない」であれば各ステークホルダーの顔を立てることができ、入試実施の実務にも無理がないグレーゾーンになります。このほか、ペーパーによるインタビューも考えられます(これはかなり優れた評価方法です)。
6月に新年度版の「大学入学者選抜実施要項」が公表された後、各私立大学からどのような年内入試の制度が公表されるのか、今年は例年にも増して注目されます。そして、学校推薦型選抜であれば、募集人員は入学定員の5割を超えない範囲において各大学が定めるとされていますが、総合型選抜はこの規制の外にあるということも注目したいところです。
