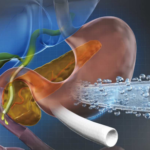医療の記事一覧
弘前大学が災害・被ばく医療センター設置、2023年度から講義
弘前大学は学内に災害・被ばく医療教育センターを設置し、2023年度から学生を対象に講義を始める。災害時に感染症患者や被 […]
アニサキスにスーツを着せてがん治療に、大阪大学が新技術開発
大阪大学大学院の境慎司教授とウィルダン・ムバロク氏(博士後期課程)らの研究グループは、アニサキスなどの線虫表面を生きた […]
高齢者介護施設における薬剤性有害事象と薬剤関連エラーのリスク実態を解明
京都府立医科大学などのグループは、日本の高齢者介護施設(以下、介護施設)における臨床疫学的調査を行い、介護施設入所者の […]
香川大学発スタートアップ、京都大学、熊本大学ら「妊娠うつ・産後うつ」の予兆検知技術を共同研究
香川大学発スタートアップで、周産期のオンライン診療プラットフォームを開発・販売するメロディ・インターナショナル株式会社 […]
慶應義塾大学、簡単な脳波計測で軽度の認知障害を早期発見
慶應義塾大学理工学部の満倉靖恵教授、グローバルリサーチインスティチュートのブライアン・スマリ特任講師らの研究グループが […]
全く新しいステントを開発、ガン患者の苦痛を緩和
東京都立産業技術研究センターは、東京医科大学、福井大学、慶應義塾大学と共同で、世界初の機能を持つ「ステント1」を開発。 […]
45歳未満の女性の肥満は乳がんのリスクが低い、東京大学が調査
東京大学大学院の小西孝明氏(医学博士課程)らの研究グループは、国内の45歳未満の女性約80万人のデータを解析した結果、 […]
世界初、近畿大学が月経前症候群(PMS)患者に特徴的な腸内フローラの分布を発見
月経前症候群(以下、PMS)は、月経前3~10日のあいだ不快な精神・身体症状が続き、女性のパフォーマンスを妨げる疾患で […]
日本の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)罹患後症状の実態 慶應義塾大学が調査
慶應義塾大学などのグループは、日本においてこれまでで最大規模(1,066例)の新型コロナウイルス感染症(以下、COVI […]
日本の子どもの歩き方は諸外国の子どもと異なる、名古屋大学などが調査
名古屋大学大学院、同大学医学部附属病院、愛知県三河青い鳥医療療育センターの研究グループは、日本の小学校児童の歩行の基準 […]