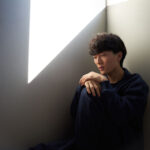国際共同研究の記事一覧
微生物で水田のメタン削減 茨城大学研究に米ビル&メリンダ・ゲイツ財団から約5億円助成
微生物を活用して水田で発生するメタンの削減を目指す茨城大学農学部の西澤智康教授らの研究に、米国のビル&メリンダ・ゲイツ […]
戦略的創造研究推進事業CREST「NARRABODY」が日仏合同1st Meetingで皮切り
明治大学の嶋田総太郎教授、東海大学の田中彰吾教授、畿央大学の森岡周教授らと、フランス国立衛生医学研究所のYves Ro […]
九州大学が「病的なひきこもり」と「健康なひきこもり」を評価するツールを開発
社会的ひきこもり(以下、ひきこもり)」は、いまや日本だけの現象ではなく、国際的に通用するひきこもりの評価基準が求められ […]
福島原発事故後の作物中の放射性セシウム濃度は長期的に低下、茨城大学などが予測
茨城大学などの共同研究チーム※は、数理モデルにより、福島原発事故後の農耕地の放射性セシウム(137Cs)は、土壌中での […]
国際研究チームが日本・スペイン・スウェーデンの自治体職員に大規模な意識調査
日本、スペイン、スウェーデンの地方自治体に関する国際研究チームは6~7月、世界初とされる大規模自治体職員意識調査を3カ国 […]
大人は子どもの認知能力獲得を学習の結果と誤認識、大阪大学などが日米で調査
大阪大学大学院の孟憲巍助教らの研究グループは、ラトガーズ大学認知学習センター、同志社大学と共同で、子どもの色の識別など […]
「長い1960年代」高度経済成長期の日伊比較、東北大学とラ・サピエンツァ大学大学がオンライン出版へ
東北大学日本学国際共同大学院とイタリア・ローマのラ・サピエンツァ大学は、高度経済成長とさまざまな社会・学生運動、文化の […]
シャーガス病感染の高リスク地域を特定、大阪公立大学などがエルサルバドル現地調査
大阪公立大学大学院(仁田原裕子大学院生ら)と群馬大学大学院の研究グループは、エルサルバドル保健省やエルサルバドル大学等 […]
卵を産む哺乳類、カモノハシとハリモグラの分析から苦味感覚の進化を辿る
北海道大学、明治大学、京都大学、アデレード大学、オーストラリア国立大学、コペンハーゲン大学などの国際共同研究チームは、 […]
北極研究推進へ、ロシア人科学者との対話必要 神戸大学がNatureに寄稿
神戸大学極域協力研究センターは北極研究の推進に向け、ロシアによるウクライナ侵攻後もロシア人科学者との対話継続の必要性を […]